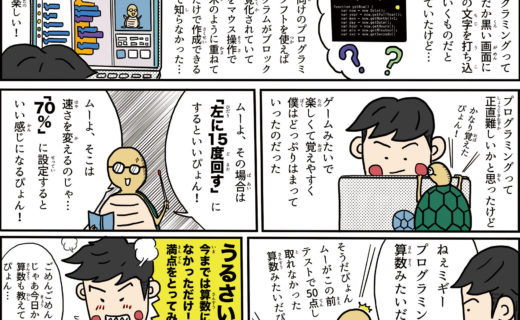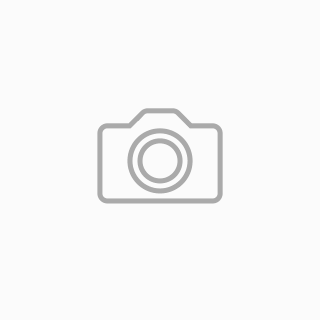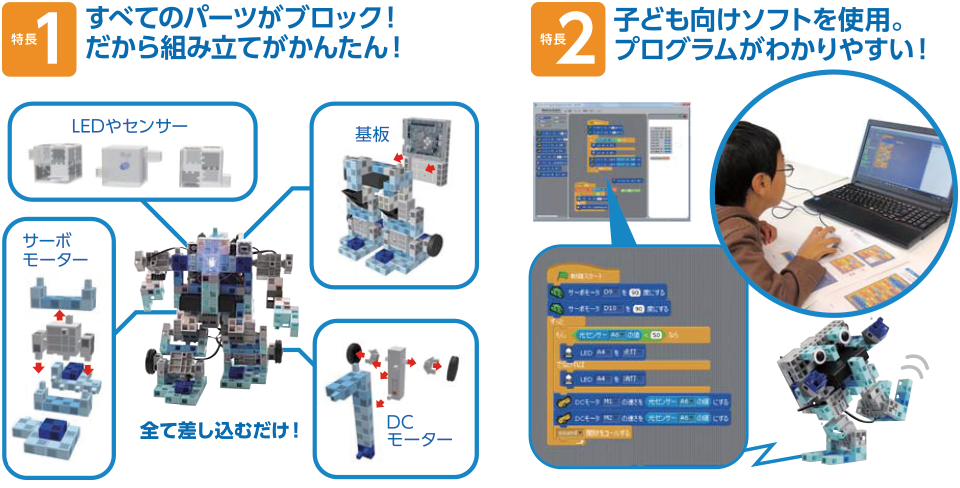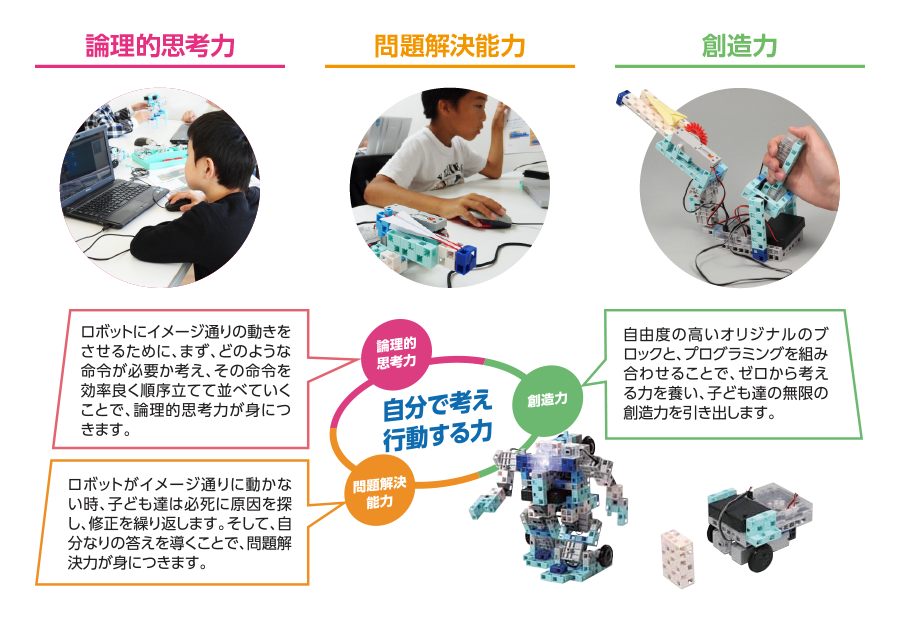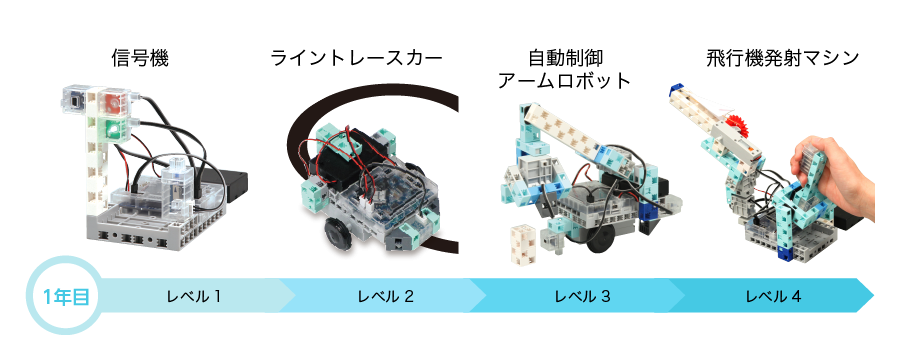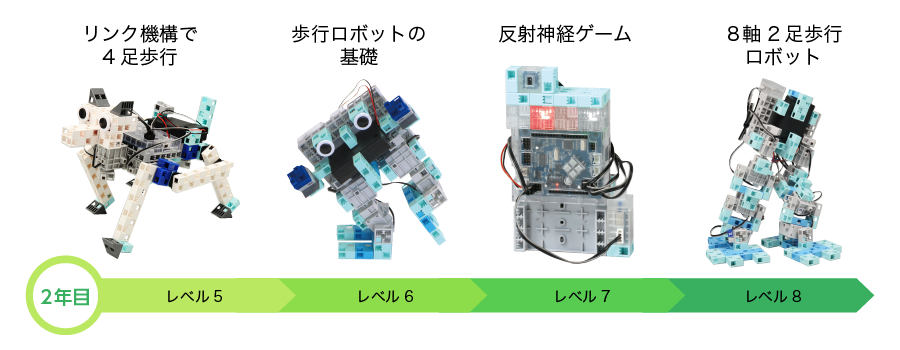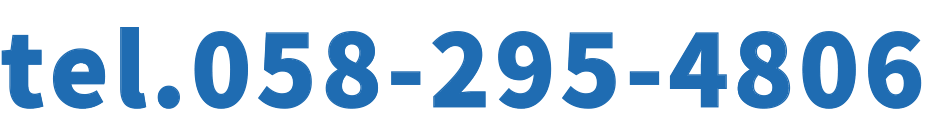こんにちは。
岐阜市長良でSTEAM教育を実践している『ながら STEAM LAB』です。
これからの子どもたちが生きるのは、AIが身近に存在する新しい時代。正解のある問いに素早く答える力だけではなく、自分で問いを立て、仲間と協力しながら新しい価値を生み出していく力が求められます。
そうした未来に向けて、家庭でもできるSTEAM的な子育てのヒントをお届けしていきたいと思います。
今や子どもたちの生活にすっかり溶け込んだYouTube。
「こんなに見せていていいのかな…?」と不安になる親御さんも多いかもしれません。
でも実は、関わり方ひとつで“ただの視聴時間”が“学びの時間”に変わることをご存じですか?
今回は、YouTubeを「受け身」では終わらせない、親子でできるちょっとした工夫をご紹介します。
「うちの子、本当にYouTubeばっかり見てて大丈夫なんでしょうか?」
多くのご家庭で聞かれる悩みのひとつです。朝から晩までタブレットを手放さず、お気に入りの動画を繰り返し見ている姿に、不安になる親御さんは少なくありません。
でも、少し視点を変えてみましょう。本当に“見ていること”そのものが問題なのでしょうか?
◆ 見る=悪ではない。問題は“見たままで終わる”こと
YouTubeは、子どもたちにとって「現代の窓」のようなものです。世界中の料理、実験、ゲーム、アート、動物、乗り物…あらゆる情報がそこには詰まっています。
つまり、YouTubeは刺激と可能性の宝庫。
大切なのは、それをどう受け取り、どう関わるかです。
子どもが「ただ受け取って終わり」という“受け身”の姿勢に留まるか、そこから何かを得て“学び”へ変えていくかは、大人のサポート次第で大きく変わります。
◆ 第1ステップ:「何を見ているか」に興味を持つ
まずは、子どもの“視聴の世界”に入っていくことから始めてみましょう。
「なに見てるの?」「それ、どんな話?」
そう声をかけてみると、子どもは「聞いてくれるんだ!」と嬉しくなり、自分の言葉で動画の内容を説明しようとします。
この“説明する”という行為そのものが、思考力・要約力・語彙力を育てる立派な学びです。
親に伝えるために、順序立てて話そうとする中で、動画で見た内容が脳内で整理され、知識として定着していきます。

◆ 第2ステップ:「見る→考える→やってみる」へつなげる
YouTubeを“学びの入口”に変えるには、視聴後の声かけがカギになります。
たとえば料理系の動画を見ていたら──
「これ作ってみる?」と一緒にキッチンへ。
ゲーム実況が好きなら──
「自分ならどんなステージを作ってみたい?」とマイクラやロブロックスに誘導。
DIY動画なら──
「家にも材料あるかも」と、一緒に段ボールを取り出して試してみる。
このように、“手を動かす”体験に結びつけることで、YouTubeは「受け身」から「創造の起点」へと変わります。

◆ 第3ステップ:「一緒に楽しむ」ことが最大の学び
子どもが夢中になっているものを、親が一緒に楽しもうとする姿勢は、子どもの自己肯定感にもつながります。
「これってすごいね」「教えてくれてありがとう」
そんな言葉ひとつで、子どもは「好きなことを話してもいいんだ」と感じ、自信を持つようになります。
その結果、「好き」が「探究」につながり、「探究」が「学び」に育っていく。
これが、STEAM教育でも重視される“主体的な学び”の土壌になります。

◆ 「受け身」の時間は、“学びの種”でいっぱい
私たち大人の視点では「ダラダラ動画を見ているだけ」に見える時間にも、子どもたちは実は何かを感じ取り、吸収していることがあります。
それを“ムダ”で終わらせるか、“価値ある体験”に変えていくかは、関わり方次第。
YouTubeは、本来「見たままで終わらない」ためのきっかけを無限に提供してくれるツールでもあるのです。
◆ 最後に:学びは、“好き”から始まる
子どもが夢中になっている世界には、その子だけの未来のヒントが詰まっています。
「YouTubeばかりで困る…」ではなく、
「YouTubeから、何が始まるだろう?」という視点に切り替えてみませんか?
大人が寄り添い、問いかけ、少しだけ関わることで、
その「無駄に思える時間」は、きっと「未来をつくる時間」へと変わっていきます。
右高英一
最新記事 by 右高英一 (全て見る)
- プログラミングより前に育てたい、“論理的なおしゃべり力” - 2025年6月28日
- プログラミングより前に育てたい、“論理的なおしゃべり力” - 2025年6月27日
- YouTubeばかり見てても大丈夫?ー“受け身”を“学び”に変えるヒント - 2025年6月17日